「苦くて甘い学び」AIと共に生きる力を育む、Hyper Leaders’ Boot Camp 第1期 参加者インタビュー
- 寺嶋 広明

- 2025年10月28日
- 読了時間: 9分
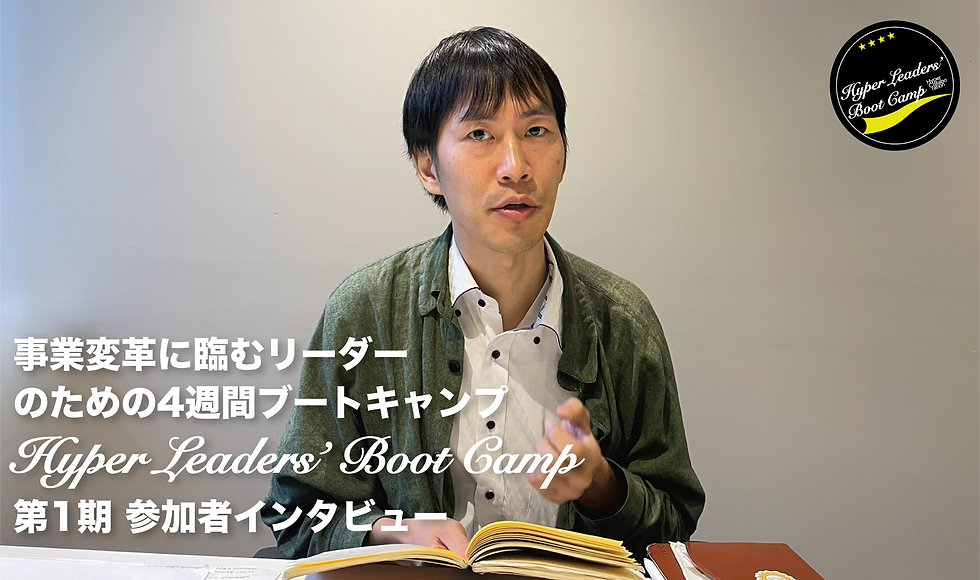
こんにちは、Hyper-collaborationの寺嶋です。
今回は、Hyper-collaborationエバンジェリストであるネスレ日本の高田さんが企画し、Hyper-collaboration代表の吉田が解説を加えるという形で実施した「Hyper Leaders Boot Camp」第1期の参加者インタビューをお届けします。
このプログラムの狙いは、Hyper-collaborationの3つの専門領域「エンタープライズアーキテクチャ」「チームマネジメント」「EQ(感情知能)」を軸に、各回7本の論文をAIツール(Gemini と NotebookLM)を活用しながら「読み・聴き・語る」ことを通じて、これからのAI時代に組織の変革を実現するリーダーに向けて、「AI時代の学び方を再設計する」ことでした。
2025年10月21日、街路樹が黄色く色づき始めた大手町で、第1期を修了された遠藤径至(えんどうけいじ)さん(厚生労働省勤務)に学びの背景や変化、そしてAIと人の共生への思いを伺いました。
厚生労働省で「働く」を支える仕事を
Hyper-collaboration寺嶋広明(以下、寺嶋):
まず、今のお仕事について簡単に教えてください。
遠藤径至さん(以下、遠藤):
厚生労働省で就労系障害福祉サービスを担当しています。
障害のある方が働きたいと思ったときに、「福祉的就労の機会を用意したり,企業での就労に向けて支援したり」するそんな制度をつくる側ですね。
以前は、ハローワークで実験的に行われている「AIを活用した職業紹介のマッチング」を担当していました。
過去の求職者と求の人データをAIに学習させ、職員が提案時に参考にする仕組みです。
「AIを使って「仕事と人」をつなぐ仕組みを設計する」いま思えば、それが自分にとって「AIと関わる最初の入口」でした。
参加の動機:「Hyper-collaborationって、面白いことをやっている」
寺嶋:今回のHyper Leaders Boot Camp(以下、Boot Camp)に参加しようと思ったきっかけは?
遠藤:もともと、Hyper-collaboration(以下HYC)さんのイベントには何度か参加していて、「ここは何か面白いことをやっている組織だな」と感じていたんです。
キャリアコンサルティングの業務を担当していた時に組織開発に興味が湧いてそこから辿って、HYCにたどり着いたんですが、HYCは安易に「組織開発をやっている」とは言っていない。
いろんな要素を組み合わせて独自の方法論にしているところが魅力でした。私が組織開発に興味を持っているところ似ているような気がして琴線に触れました。情報設計に関しても同じ感じですね。
しかも、今回は個人で参加できる。大学院のような選抜もなく、「時間とお金を自分で確保できれば入れる」それが、すごく健全で、ワクワクするなと思いました。
AIと共に生きる「自然さ」
寺嶋:全4回のセッションで特に印象に残ったことはありましたか?
遠藤:やっぱり第1回のキックオフですね。
AIをテーマにしたセッションで、冒頭から高田さんのお話に引き込まれました。それまでAIは「業務効率化のためのツール」くらいにしか思っていなかったんです。でも話を聞いているうちに、「これはもう、学び方や価値観そのものに関わる話なんだ」と気づかされました。
寺嶋:視点ががらりと変わった、と。
遠藤:そうです。
ハローワークでの件もあり、それまで「AIを使っていかなきゃいけないようね」くらいの世界にいたんですが、バーンと壁が壊れて全然違う世界が見えたというか。そもそもの世界観とか、価値観とか、学習観に関わってくることなんだって。そもそもAIに興味があって受講を決めたというわけではなかったので、ガツンとぶん殴られたような衝撃でした。AIを拒むとか、距離を取るとかではなく、自然に受け入れること。
AIが世の中にあふれているなら、それを避けるより、一緒に考え、使い、学ぶほうが自然だと感じたんです。
「苦くて甘い」AIとの関係に感じたリアル
寺嶋:Day1のふりかえりでの発言、「苦くて甘い」という言葉が印象的でした。
遠藤:AIの可能性を感じると同時に、思い通りに動いてくれない「もどかしさ」もある。
「ああ、これは『苦くて甘い』関係なんだな」
と、ふっと言葉が出ました。
AIを使う可能性、ワクワク感が「甘さ」なんですけど、一方、もうまくいかないことも多くて、最初はストレスにも直面しそうだなと感じていました。
でも、その「苦さ」ごと受け入れて一歩進む決意をしたんです。
今まではちょっとそういうのがあったら、もうめんどくさいからいいやみたいなぐらいの温度感だったんですけど、あえてネガティブな未来みたいなことを先取りすることで、いざそれが来た時にも、「その苦いのが来るのは分かっていたよ、でもその先に行ってみようと思ってるんだよ」っていう乗り越える決意。みたいなことを連想して「苦くて甘い」という言葉が出ました。
寺嶋:その「決意」を後押ししたのは何だったんでしょう。
遠藤:焦りというよりは、「自然に生きたい」という感覚でした。この時代にAIを避けて生きるのは、「首を真横に向けたまま生きるようなもの」だなと。だから、怖がるよりも、付き合い方を学ぶほうが自分らしいと思ったんです。「これはもう、仕事の延長じゃない。自分のこれからを生きるための学びなんだ」という思いが心の中で湧き上がってきていました。
「ツール」と「相棒」のはざまで
寺嶋:その後、3週間AIツールを使いながら学んでいく中で、何が変化しましたか?
遠藤:テクニカルな変化と、価値観の変化の両方がありました。
技術的なほうでは、NotebookLMやGeminiを使っているうちに、少しずつ「相棒感」が出てきたんです。
最初は「使い方を覚えなきゃ」と構えていたけど、回数を重ねるうちに「プロンプトを変えてこう聞いたら、こう返してくれる」「AIってここは苦手なんだな」と、人付き合うようにAIとの関係性が見えてきました。そう、まるで「仲良くなっていく」ような感覚がありました。
「雑につまみ食いでも、厚く学べる」
寺嶋:では価値観の変化についても聞かせてください。
遠藤:学習感みたいな話で言うと、結構雑につまみ食いした感みたいな。
参加者の誰かが「こんなに雑に本を読んだのが久しぶりだ」みたいなことをおっしゃってたと思うんですけど、「雑につまみ食いしてもいいんだ」というか。
今までだと雑につまみ食いしてもあんまり得られるものが少なすぎて、学びには繋がっていなかったんですけど、AIの力を使うと「雑につまみ食いしてるのに結構肉厚なインプットが得られる」とか。本を詳細に全てを読まなくても、要点を押さえてディスカッションしたり、気になったキーワードだけを掘り下げたり。しかも、それがちゃんと自分の知識として残っていく。その結果、自分の学びの「アリ」の範囲が広がったみたいな、柔らかくなったみたいなのはあったと思いました。「AIを介すことで、学びの『雑さ』が『自由さ』に変わった」、そんな感覚がありました。
寺嶋:本って読み切らないと罪悪感が湧いたりしますよね。
遠藤:そうですね。今までは「読み切らなきゃ」という強迫観念がありました。
でも今は、3章まで読んだ時点で「この本からはこれを受け取った」と思えればそれでいい。後で続きを読むかもしれないし、読まないかもしれない。
でも、今得たものがあるなら、それはもう学びとして完結している。
「理解できない部分を一度置いておく」
そんな余裕が生まれたのは、AIと学ぶ体験があったからだと思います。
別の言い方をすると、読書の目的が明確になったということかもしれません。
ある目的を叶えるためにこの本を読み始めることを決めけたど、実際読んでみて、同じ関心からこの本とちょっと違ったところとか、この本で前提になっててそんなに触れられてないこの概念も気になると、ちょっと一旦ページを閉じ、そこに立ち寄って、学んでからの方がこの本にちゃんと理解できるんじゃないかということを思いついたら臆せず一旦ストップしてそっちに行くことができるようになりました。
仕事の中でAIが「制度の家庭教師」に
寺嶋:では、この学びが仕事にどう活きていますか?
遠藤:とても実践的に活きています。
いま担当している制度関連の資料や法律って、何百ページもあるんです。でもそれらは公に公開されている情報なので、NotebookLMに読み込ませて「家庭教師」にしています。
「この制度とあの制度の違いは?」
「この条件だけが違う理由は?」
そういう質問を投げると、関連条文や審議会の議事録まで引っ張ってきてくれる。AIが、自分の理解を支えてくれる「相棒」になりました。
寺嶋:まさに、制度を「理解する仕組み」を自分でつくっている感じですね。
遠藤:そうですね。人に聞くより早く整理できることも多くて。
あと、自治体ごとの取り組み事例を調べるときもGeminiが便利です。「〇〇県ではこういう事例があります」みたいに教えてくれるので、全国の動きを俯瞰しやすくなりました。
日常にも入り込むAI
寺嶋:日常の中にもAIが入り込んできたとお聞きしました。
遠藤:はい。
たとえば移動中、以前は音楽を聴いていた時間に、今はNotebookLMの音声で要約を聞いています。あと、「Gemini Deep Research」を使って、3日に1回くらいは気になるテーマを掘るようになりました。
「自転車のこと、意外と知らないな」と思ったら、そのテーマでリサーチしてみる。
そうやって、日常の「空き時間」が小さな探究の時間に変わる。仕事と関係ないテーマでも、知ることが楽しくなりました。
変化は「大きなブレイクスルー」ではなく、「小さな入れ替え」
寺嶋:それはまさに、生活そのものが「学びの場」になっている感じですね。
遠藤:そうですね。劇的な変化というより、日々の24時間を形成する小さなブロックが少しずつ入れ替わる感じです。ニュースを読む時間が減って、AIに話を聞く時間が増えたり、読書の向き合い方が軽やかになったり。
それが積み重なって、気づいたら「学びの地図」が少し広がっている。そんな実感があります。
「好奇心にフタをしている人」にこそ届けたい
寺嶋:このHyper Leaders’ Boot Campを、どんな人に勧めたいですか?
遠藤:うーん……好奇心にフタをしている人ですかね? ワクワクするものがあるのに、それを押さえ込んでいる人。あるいは、くすぶって火が消えかけている人。
「もう一度、火を入れる空気をもらえる場所」
それが、このHyper Leaders’ Boot Campだと思います。
参加してみて感じたのは、ここは「勉強する場」というより、「問いを再び持ち直す場」なんです。AIというテーマを通して、自分の中の興味や感性をもう一度再起動できる。それがすごく新鮮でした。
寺:これ言いたかったのに僕が聞いていないことがあったりしますか?
遠藤:仲間内の読書会でネガティブ・ケイパビリティの本を読んだことがあって、それが自分の中でBoot Campで学んだこととつながった感があります。ネガティブ・ケイパビリティは曖昧なものに対して、はっきりしないまま持ち続けるみたいなキャパシティだと思うんですけど、
今回のBoot Campで学んだ「苦みがあるけど甘みもあって、そして倒れずに進んでいける」みたいなのとつながるんです。すごい抽象的なんですけど(笑)

寺嶋より
遠藤さんの話を聞いていて、何度も印象に残ったのは「自然さ」という言葉です。AIというと特別なもの難しいものと捉えがちですが、遠藤さんにとっては「いま、ここにある現実をどう自然に受け止めるか」という問いなんですね。
「AIを拒むより、自然に受け入れて共に生きる」「雑に学ぶことが、厚く生きることにつながる」
この言葉たちは、まさに変化のただ中を生きるリーダーの姿そのものでした。HYCの目指す真の変革を実現するためには新たな学びをAIと共進め、新しい時代にどう「苦味と甘み」の双方を噛み締めながら生きていくことなのだと実感させられました。
次の第2期では、さらに多様なリーダーたちがこの「苦くて甘い学び」を共有し、新しい未来を描くことを期待しています。


